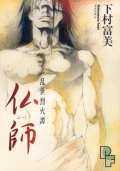 下村富美
下村富美
Fumi Shimomura
「仏師」
- 出版社:小学館
- シリーズ:プチフラワーコミックス
- ISBN:ISBN4-09-172222-9 C9979
- 価格:505円+税
- 初版発行:1999/09/20
- 判型:B6
オスマントップページに戻る
下村富美の描線は美しい。登場する人物、そして背景などはシャープでかつ端整な線で緻密に描かれる。しかし、線は多くない。質感を出すために必要な線を選び出し、そして不必要な線は大胆に省略されている。だから、整理された美しい画面になっている。実際、少女漫画雑誌掲載作品で、これだけ硬質でしっかりとした造形を持った絵を描く人は稀だ。そして下村富美の特徴として挙げられるのが、「ゴツゴツしたもの」を描くのがうまいということ。木や石などの静物はもちろん、武骨な男の骨格なども見事に描きこなす。老人を老人らしく描けるというのもポイントが高い。骨と皮、そしてシワを描くのがたいへんにうまいのだ。
「仏師」の舞台は、日本の戦国時代(永正二年=西暦1505年)、戦の傷痕癒えきらぬ国境の小国。主人公は巨躯の仏師・魚人(おびと)。精悍な顔立ちでなかなかの美青年である魚人だが、生まれつき顔に大きな痣があり、また彼があぶれ者どもが村を蹂躙し娘たちが犯されたときにできた子だったこともあり、村人からは敬遠された。しかし、仏を彫る腕は確かで、魚人の彫った仏には病を治す力があるといわれていた。そんな魚人がある日、領主の妻にして「死神」と呼ばれる姫・耶十(やと)と出会う。悪名高き姫の姿を一目見た魚人は魅了され、屋敷に乗り込み、彼女の姿を彫らせてくれと懇願する。そして、満足行くものができなかったら命をもらうという姫との約束のもと、魚人は彫り始める。
魚人はなぜ仏を彫り続けるのか。仏とは木の内にあり、彫る側はそれを取り出してやればよい、と魚人は語る。彫ることにより、己の生、業を見出そうとする彼の姿は、不器用だが恐ろしいほどに真摯である。その彼を心配そうに見つめる幼馴染みの女、阿トリ。そして不吉な影を瞳に宿した耶十姫。魚人を導く和尚の慈円。これらの人々の思惑がそれぞれに錯綜しながら、物語は進んでいく。そしてラストシーン。さまざまな出来事の末、仏像は完成する。彼が掘り出した仏像が、光の中に溶けていくような描写の中で佇むシーンは、静謐で崇高な感動を呼び起こす。
下村富美の表現には力がある。描写に説得力がある。ストイックで土性骨が据わっている。ちょっと珍しいぐらいに。
なお、下村富美の既刊単行本には、「仏師」のほかに以下の「首」という短編集がある。表現としては、「仏師」のほうが一段上のレベルにあるが、機会があればこちらもぜひ。
 「首」
「首」
- 出版社:小学館
- シリーズ:プチフラワーコミックス
- ISBN:ISBN4-09-172221-0 C9979
- 価格:500円(本体485円)
- 初版発行:1997/01/20
- 判型:B6
- 収録
- 「花狂ひ」
- 「蝶の墓」
- 「首 KUBI」
- 「水神」
- 「birds バーズ」
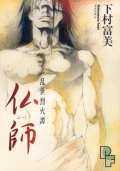 下村富美
下村富美 「首」
「首」